|
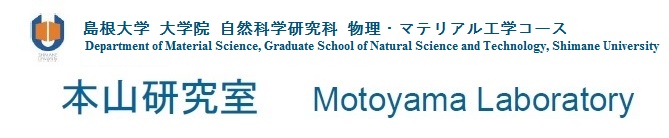








研究内容
生物は、 外見の形状や機能などの特徴を根拠に様々な種族に分類されます。
例えば、 「 松 」 は裸子植物のマツ科に属しているとか、 「 キリン 」 は脊椎動物の哺乳類の鯨偶蹄目キリン科に属して
いるなどです。 この分類は、 その生物がどのような点で特徴的であるのかを理解するのに非常に助けになります。
さらに、 外見などの特徴から分類したにもかかわらず、 この分類が生物の進化と関係が深いこと、
遺伝子の相関性とも関係が深いことなど、 興味深いことがたくさんあります。
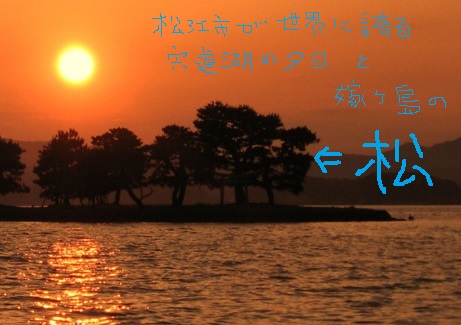 
|
物質ではどうでしょうか?
物質について研究している私たちも同様に物質を分類し、 理解を
深めようとしています。金属、 半導体、 絶縁体の分類や、
強磁性体、 反強磁性体、 ・・・ など、物質の様々な特徴から
分類を試みています。
しかし、 「 クジラ 」 は、 水の中で生活していますが魚の
仲間ではなく、 「 イヌ 」 や 「 ヒト 」 などの哺乳類
の仲間であるように、 物質においても正しく分類することは
難しいことです。
|
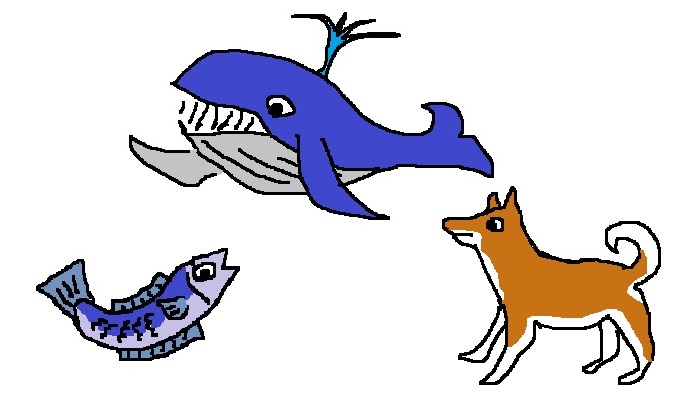
|
鉛筆の芯 ( 炭素 : グラファイト ) は、 電気が流れますが、金属でしょうか?
金属には、 独特の金属光沢があり、 軟らかく延性 ・ 展性などの性質があるはずですが、 鉛筆の芯にはこれらの性質は
なさそうです。 「 そうか! 半導体だ! 」 と簡単に終わりにしないで下さい。
電気が流れる ・ 流れないには、2つの分類しかありません。 半分流れると言うのは、いまいちよくわかりません。
それから、 「 人間って金属じゃないよね、 でも、 電気流れるんじゃね? 」 って、 思ったことありませんか?
|
( ※ 分類には明確な判断基準があります。 そして、
性質にもはっきりと違いが現れます。
金属 ・ 半導体 ・ 絶縁体の違いは室温付近で
電気抵抗を測定するだけでは、 不十分で、
十分に低温で測定する必要があります。 )
|

|
物質には、 金属 ・ 半導体 ・ 絶縁体、 誘電体、 磁性体、 超伝導体、 様々な物質群があり、 それらの中でも、
さらに多種多様です。 この多種多様な性質はその物質を構成する元素とその元素にふくまれる原子核と電子によって
決定されます。 電磁気の力で強く結びついた原子核と電子たち、 彼らの集団運動を理解するためには、
電磁気学だけでなく、量子力学 ・ 熱力学 などの様々な考え方を必要とします。
物質の中ではどのような世界が実現しているのでしょうか?
絶対零度に近い温度はどのような世界になっているのでしょうか?
物質の性質を様々な観点から研究するのが、 物性物理学であり、 私たちの研究内容です。
新しい物質の発見は、新しい材料の開発につながります。
電子の振舞いを理解するための理論が、宇宙や素粒子の世界を理解するためのヒントになることだってあります。
|
研究テーマ
 「 磁性と超伝導の共存する重い電子系化合物の研究 」 「 磁性と超伝導の共存する重い電子系化合物の研究 」
 「 空間反転対称性を欠いた結晶構造中の超伝導の研究 」 「 空間反転対称性を欠いた結晶構造中の超伝導の研究 」
 「 新奇な重い電子系化合物の探索 」 「 新奇な重い電子系化合物の探索 」
 「 点接合分光測定による重い電子状態、超伝導状態の観測 」 「 点接合分光測定による重い電子状態、超伝導状態の観測 」
 「 寒剤としての液体ヘリウムを必要としない冷凍機の開発 」 「 寒剤としての液体ヘリウムを必要としない冷凍機の開発 」
|
技術
※注
Motoyama lab., Shimane Univ.
|